ジブリの『ゲド戦記』を久々に観た。初回が封切り直後の映画館、2回目は数年後の金曜ロードショー、3回目が一昨日の金曜ロードショー。最初の頃と受ける印象がかなり違った。
封切り当時、ネットでの評判は散々だったのを覚えている。
宮崎吾朗氏が初監督。父親・駿氏との比較対象となることは免れず「技巧があまりに稚拙」「主人公のキャラクターが暗すぎる」「ストーリーが平板」等々。私も最初から吾朗氏が宮崎駿氏の息子であるという認識から入ってしまい、つい父親の作品と比べてしまった(絵柄もキャラのモチーフも父親の作品を彷彿とさせるのでなおさら)。
確かに技巧的なもの、テクニック的なことについては未熟さがある印象は受けた。しかし、この作品は上手いとか下手とかエンタメとしての完成度といった世間的な評判を超えた、本質的なテーマを孕んでいると確信する。
生きていくことへの恐怖
物語は、主人公青年アレンの父親殺しから始まる。殺した後父親の剣を奪い家を飛び出る。彷徨う中、ある晩見た夢の中で彼は沼地を歩いているが、ぬかるみに足が取られてしまい、死んだ父親が目前に迫ってくるシーンは強烈で、まさに当時の私の心象風景とぴったり重なった。
当時30代半ばだった私は、都会生活に託した夢が破れて地元に戻り、経済的自立を果たすため、実家を拠点に別の道を歩みはじめていた頃だった。その選んだ別の道というのが自分で決めておきながらも、憂鬱と焦燥感と自己嫌悪だらけの毎日。ここから逃げ出したくてしかたないけど足がぬかるみにとられているような感覚。この先私は自分の人生を切り拓いていけるのか?自分が自分であること、弱さや狡さも含めたありのままの自分に直面する恐怖。生きていくのがしんどい。いっその事この世から自分を消し去りたい。
主人公の青年アレンの心の葛藤は、他人事ではなかった。
同時にこれは紛れもなく吾朗氏が自身をアレンに投影していると直感した。氏の父親はアニメ界の巨匠としてあまりに偉大で。父親との確執と自己を確立しようと苦しみもがき、父を踏襲しながらも父を乗り越えようと懸命に踏ん張っている。そんな氏の切実な想いが強烈に私の心に流れ込んできた。
そして今回、久々に観たが、初めに観た時よりもさほど技巧的な稚拙さといった部分が気にならなかった。それよりも、氏はどういった想いを抱えて制作に向き合ってたのだろう、というシンパシーを強く感じた。
同時に、ストーリー中のキーワードが、最近私が学んでいる西洋占星術の思考や概念とシンクロしていた。
あと印象的だったのが、舞台の時代設定で「疫病が流行って世界が荒み、貧しい人間が奴隷という商品になっている」「世界の均衡がとれなくなりつつある」といったくだりだ。まさに今現在の世界と重なっている。
言うまでもなく父・駿氏の作品も私は好きだ。ただ、駿氏は高度経済成長期とともに駆け抜けてきた世代ということもあってか、主人公のキャラ設定が「根っから真っ直ぐで正義感がある」イメージが主流だ(特に初期の頃)。対して吾朗氏はその後の世代。生まれた時から物質的な豊かさは恵まれているものの、右肩上がりの経済成長は翳りが見えてきて、大きな目標を見失った世代だ。彼の描くアレンはデフォルトからなんと陰鬱で堕落的なことか。最終的にはハッピーエンドを迎えはするものの、そこに至る過程では、誘惑に負けてあやうく薬物に手を出しそうになったり、邪悪な魔法使いの言うまま薬を飲んで魂を操られてしまったりと、自らのうちに潜む「影」にひきずられ翻弄されている。
父・駿氏と私の父親がほぼ同じ年齢なのと、吾朗氏と私が5歳しか違わないことも、世代的な意識の方向がシンクロしているのかも知れない。
『ゲド戦記』の魅力。哀しみを伴う音と色彩、主人公の陰鬱なキャラ
世間的には酷評されてきた印象の強い『ゲド戦記』ではあるが、この作品独自の魅力を私は声を大にして伝えたい。それは駿氏の作品にはない吾朗氏の作品ならではの魅力ともいえる。
第一に、音楽のセレクトの秀逸さだ。BGMが洋画調の要素がふんだんに取り入れられしっくり馴染んでいた。そして何よりもヒロイン役であるテルーの声優もつとめた手嶌葵の主題歌が実に素晴らしい。今まで私はこの曲にどれだけ涙し支えられたことだろう。
第二に、背景(建造物や自然風景)の精緻さはジブリならではだが、ストーリーとあいまって色遣いがなんとも繊細に感じられた。第一に述べた「音」とあわせて「色彩」を通じて繊細で切実な哀しみが伝わってくる。これは駿氏の作品とは明らかに趣を異にする。
第三に、アレンの徹底的に陰鬱なキャラがむしろ魅力的に映るのだ。生きていくことに対する不安と恐怖に駆られた彼の表情は、下瞼と口の脇の法令線が異様に目立つ。余りにぶざまとしか言いようがない。クライマックスでは賢者ハイタカの胸に抱き止められ涙を流すシーンがあるが、滝のような涙と共に鼻水もシッカリ出てくる描写が斬新だ。(実際に嗚咽する時って鼻水すごく出るよなって納得)それまでのジブリの主人公像の明朗快活で基本前向き、といったキャラの真逆をいっている。不安と恐怖に怯えたり、絶望に打ちひしがれてぐったりと虚無感を漂わせているあたりが、人間の本音が率直に表現されていて好感が持てるのだ。
父・宮崎駿氏が目指していたのは’自分の外側=世界を変えていくファンタジー’であり、観客をワクワクドキドキと高揚させる視点を決して外さないエンターテイメントなのに対して、息子・宮崎吾朗氏が目指していたのは’自分の内側にとことん向き合う文学作品’に近いものだったのではないか。
世間で酷評されていた内容は、それはそれで一理あるかも知れない。地味で暗くて一般受けはしない、親の七光りに頼っただけ、などと評されてもなお、むしろその欠落や未熟さ自体がこの作品の魅力となっている。誰からどんなに揶揄されようが一つの作品として形にし世に出された事実に、胸を打たれるのだ。




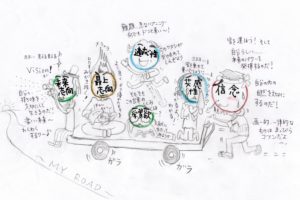







コメントを残す